個人的な読書日記です。
「ジャンル」は出版社や書店によるもの、もしくは独断により分類しました。
「評価」は自分のお気に入り度です。
「▶あらすじ続き」「▶感想」にはネタバレを含みますので、非表示にしています。ご了承の上、クリックまたはタップしてお読みください。
画像はすべてイメージ画像です。実際の映像とは関係ありません。
作品情報
タイトル:盤上の向日葵
著者:柚月裕子
出版社:中央公論新社(中公文庫)
発行:2020年9月
初刊:2017年8月(中央公論新社)
ジャンル:推理小説,ミステリ,警察小説
評価:★★★☆☆
登場人物
佐野直也(さの なおや)
埼玉県警大宮北署地域課所属の新米刑事。30代前半。
かつて奨励会員だったことから命じられて石破と組む。
石破剛志(いしば つよし)
埼玉県警捜査一課の中堅刑事。44歳。
口が悪く煙たがられているが、刑事としての腕は第一級とされる。
上条桂介(かみじょう けいすけ)
若きエリート棋士。6段。33歳。
東京大学卒業後、就職した外資系企業を辞めて起業。大成功を収めた。
その後、突如実業界を引退し、将棋の世界へ。アマチュアのタイトルを総なめにし、新人王の座に就く。
奨励会に入会はしていないものの、あまりの実力ゆえに特例で受けたプロ試験に合格した。
「炎の棋士」の異名を持つ。
上条庸一(かみじょう よういち)
桂介の父親。長野県諏訪市の味噌蔵で職人として働く。
妻の死後、酒と賭け麻雀にはまり込み息子の養育を放棄した挙げ句、暴力を振るっていた。
長じて成功した桂介につきまとい、金を無心している。
上条春子(かみじょう はるこ)
桂介の母親。精神を病んでおり、桂介が小学校二年生の冬に亡くなる。
唐沢光一朗(からさわ こういちろう)
長野県諏訪市の元小学校校長。小学生の桂介に将棋を教え、父親の虐待から救おうとする。
初代菊水月作の駒は、元は唐沢が所有しており、桂介に贈ったもの。
唐沢美子(からさわ よしこ)
光一朗の妻。
子供を望んだが恵まれず、桂介を息子同然に思い愛情を注ぐ。
東明重慶(とうみょう しげよし)
歴代最強と謳われる真剣師。元アマ名人。「鬼殺しのジュウケイ」という二つ名を持つ。
角館銀次郎(つのだて ぎんじろう)
岩手県遠野市の旅館「語り部の宿」を営む愛棋家。東北一帯の真剣師と繋がりがある。
東明に手合いをつけ、初代菊水月作の駒を買いとった。
壬生芳樹(みぶ よしき)
若き天才棋士。竜昇。24歳。
7つのプロ棋戦のうち王棋位を除く六冠を保持し「名人になるために生まれてきた男」と呼ばれる。
桂介と竜昇戦において対決。第7局の最終戦にもつれ込んだ所から本作品は始まる。
用語集

奨励会
制度が幾度か変わり形態も複雑なため、ざっくり説明する。
日本将棋連盟のプロ棋士養成機関。正式には「新進棋士奨励会」だが、単に「奨励会」と呼ばれることが多い。
関東奨励会と関西奨励会の2つに分かれており、二段まではそれぞれの奨励会の中で対局する。
入会試験は年に1回。受験資格は試験が行われる年の8月31日時点で満19歳以下、かつ日本将棋連盟の正会員を師匠として受験の推薦を得た者とされる。
受験の推薦を得るには優れた実績を積み、実力を認められなければならず、受験可能な最下位である奨励会六級でもアマチュア三~五段程度の実力に相当する。
16歳以上では受験級位に制限がある上、奨励会に入会しても厳しい年齢制限があり、満21歳の誕生日までに初段、満26歳の誕生日を含むリーグ終了までに四段(プロ棋士)に昇段できなかった場合は原則退会となる。
作中では「満21歳」が「満23歳」とされているが、これはWikipediaによると2002年度以前の奨励会試験合格者の場合のみ。
タイトルの名称が架空の「王棋」とされていることなどから、あえて正確な情報にしていない可能性もある(こちらの不勉強であれば申し訳ない)。
真剣師
賭け将棋、賭け麻雀といったテーブルゲームの賭博によって生計を立てている者を指す。大会やタイトル戦に出場して賞金を得るプロとは異なる。
麻雀の真剣師は「裏プロ」、将棋の真剣師は「くすぶり」ともいう。
将棋の場合、将棋指しが現れたのは室町時代後期とされているが、真剣師がいつごろ現れたかは定かではない。
江戸時代、明治時代は賭博が原則として禁止されていたが、賭け将棋は盛んに行われていた。
プロを負かす実力者やプロ編入が認められる者もいたが、取り締まりが厳しくなった社会背景もあり、昭和50年代には真剣師はほとんどいなくなったとされる。
東明重慶のモデルはアマ最強と呼ばれた真剣師、小池重明(こいけ じゅうめい)と思われる。
「新宿の殺し屋」「プロ殺し」などの異名を持ち、母親は自宅で客の相手をする娼婦、結婚後トラック運転手として生計を立てていたなど、多くの共通点が見られる。
小池重明は重度の肝硬変により痩せ衰え、最期は繋がれたチューブを自ら引きちぎって亡くなったと言われる。
錦旗島黄楊根杢盛り上げ駒

読みは「きんき・しまつげ・ねもく・もりあげ・こま」。
身元不明の白骨死体とともに発見された最高級品の将棋の駒。およそ六百万の値とされる。
「錦旗」…駒に書かれる書体の一種。
「島黄楊」…御蔵島(みくらしま)産黄楊材。通称「島黄楊」と呼ばれる。薩摩黄楊と並び将棋駒の素材としては最高峰。
「根杢」…樹木の根本部分の杢目。一本の樹からわずかしか採取できず希少価値が高い。
「盛り上げ」…駒生地に彫った駒字を漆で埋め、さらに漆を重ねて盛り上げる製法。最も手間がかかり、駒師の技術が求められる。
初代菊水月(しょだい・きくすいげつ)
本作品において重要な役割を果たす将棋駒の製作者。架空の人物。
作中では「江戸後期から明治にかけて活躍」し、「景山、静風とともに、三大名工と呼ばれている」とされる。
「菊水月」という名は、今も健在の実在する天童将棋駒伝統工芸士「掬水(きくすい)」から採ったのではないだろうか。
掬水も錦旗本黄楊根杢盛上の駒を製作、販売店では駒袋なしで税込52万円の値がついている(現在は売り切れ)。
フィンセント・ヴァン・ゴッホ(Vincent Willem van Gogh)
1853年生まれ、1890年37歳で死没。オランダのポスト印象派の画家。
弟テオドルス(通称テオ)の援助を受けながら画作を続けたが、生前に売れた絵は1枚のみだったと言われている。
その生涯は多くの伝記や、映画『炎の人ゴッホ』に代表される映像作品で描かれ、通称「炎の画家」とも呼ばれる。
代表作のひとつ「ひまわり」は晩年のアルル時代に盛んに描かれており、「花瓶に挿された油彩の絵画」は7点(6点が現存)、パリで制作されたものも含め「花瓶に挿されていない」絵も併せると合計11点(または12点)とされる。
作中で桂介が最も好む「十二輪の向日葵」は2点存在しており、制作時期も構図もほぼ同じのため、どちらを指すかは判然としない。
「画集の表紙に部分的に使われていた」という設定だが、実在する画集に「ひまわり」が使われる場合、調べた限りでは花15本の作品が多かった。
あらすじ

平成6年(1993年)夏、埼玉県の天木山で身元不明の白骨死体が発見された。
遺留品は7組しかないと言われる名匠・初代菊水月の将棋駒。
埼玉県警のベテラン刑事・石破と、かつてプロ棋士を志した新米刑事・佐野は、駒の足取りを追い日本各地を飛び回る。
折しも将棋界では、実業界から転身した異端の革命児・上条桂介六段と若き天才棋士・壬生芳樹竜昇の対決が行われ注目を集めていた。
作中では2人の刑事を軸にした現在と、桂介の幼少期から成長を軸にした過去が交互に語られる。
 | 盤上の向日葵(上) (中公文庫 ゆ6-1) [ 柚月 裕子 ] 価格:770円 |
 | 盤上の向日葵(下) (中公文庫 ゆ6-2) [ 柚月 裕子 ] 価格:748円 |
あらすじ続き

以下はネタバレを含みます。ご了承の上、▶をクリックまたはタップしてください。
こちらをクリック
昭和46年(1971年)、長野県諏訪市。
小学校3年生の桂介は、母を亡くし父・庸一に虐待を受けていた。
将棋が趣味の唐沢は、古紙回収に出した将棋雑誌を桂介がこっそり持ち帰っていることを知り、一緒に将棋を指すようになった。
唐沢夫妻は桂介を慈しみ、桂介の尋常ではない将棋の才能も見出した。
虐待からも救おうとし、奨励会も勧めたが、庸一の執着により断念せざるを得なかった。
月日は流れ、頭脳明晰な桂介は現役で東大に合格。
死期を悟っていた唐沢は、大切にしてきた初代菊水月作の駒を餞別として桂介に贈った。
上京した桂介は庸一と縁を切り自活していたが、将棋への情熱は断ちがたかった。
そこへ真剣師・東明と出会う。
金に汚く人間性はろくでもない東明だが、将棋の腕は誰もが認めるところだった。
桂介は東明に搦めとられるように、初代菊水月作の駒を持ち東明との旅打ちに同行する。
東明に騙され、駒を勝手に角館に売り飛ばされた桂介は、必ず買い戻すと懇願。
大学卒業後、外資系企業で必死に金を貯め、約束を守ってくれた角館から駒を買い戻した。
その後、独立してソフトウェア会社を立ち上げ大成功した桂介の元へ、庸一が金の無心に何度も現れるようになる。
さらに東北の旅打ち以来、行方をくらましていた東明までもが8年ぶりに訪ねてきて、将棋を指すことに。
余命幾ばくもない東明は、駒の借りを返すために人殺しでも何でもしてやると冗談めかす。
庸一の再三の無心に堪りかねた桂介は諏訪に戻り、手切れ金を渡して縁を切ろうとするがうまくいかず、それどころか桂介は庸一の実子ではないと聞かされる。
母の春子は島根県の老舗の味噌蔵の出だったが、実兄・彰浩と通じて桂介を妊娠。彰浩が自殺した後、春子は自分に岡惚れしていた奉公人の庸一に駆け落ちを持ちかけた。
諏訪に移り、出産してからは元気を取り戻した春子だったが、桂介が成長するにつれ彰浩に似てくると、精神を病んで自殺した。
出生の秘密を知り、大学時代に出会ったゴッホの「ひまわり」に心を掴まれた理由を理解してから、桂介は盤のマス目に向日葵を見るようになった。
最後まで消えない向日葵が咲くマス目が、自分の狂った血が求める指す手なのだと。
同時にわき上がる死への希求に、桂介は庸一より先に死ぬことはできないと、東明に庸一殺しを依頼する。
平成6年(1993年)12月、山形県天童市。
壬生と桂介の対局は、時間上では桂介が圧倒的に有利だったにも関わらず、向日葵の咲かなかった桂介はまさかの反則負けを期した。
翌日、佐野と石破が張り込む中、桂介は東京行きの始発に乗り込んだ。
そして3年前を思い起こしていた。
庸一殺しを依頼して半年後、「約束を果たした」と連絡してきた東明は天木山に連れていくよう桂介に頼む。
かつて東明が短い間だったが、人間らしい暮らしをした麓の町を見下ろしながら、初代菊水月作の駒で桂介と東明は勝負する。
負けた東明は自分で腹を刺して果て、桂介は望み通り遺体を埋葬すると、名駒を香典に東明の胸に抱かせた。
東京駅に到着した桂介に、石破と佐野が声をかける。
上りの新幹線がホームに近づく中、銀色の雪が満開の向日葵に変わり、桂介は向日葵に向かって身を躍らせた。
感想
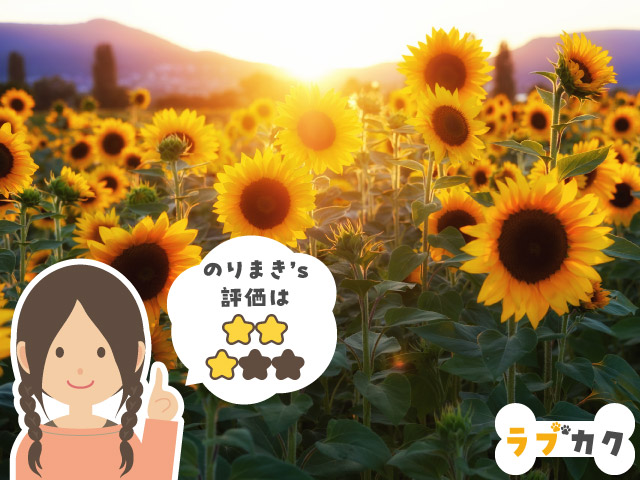
以下はネタバレを含みます。ご了承の上、▶をクリックまたはタップしてください。
こちらをクリック
柚月裕子の文章はミルフィーユのようだといつも思う。
平易な短文を丁寧に隙間なく積み重ねて形づくられる様は、読んでいて気持ちがよい。
プロの作家を並べるのは失礼かもしれないが、特に警察機構や捜査の描写は横山秀夫を思わせる。
本作品は2人の刑事による捜査(現在)と、上条桂介の幼少期から成長(過去)が交互に章立てされており、さらにミルフィーユの印象が強かった。
和菓子ではなく洋菓子なのは、ロングヘアをハーフアップにし、洋装と呼ぶのが相応しそうなクラシカルないで立ちの著者近影のせいだろう。
将棋はよく知らない
私自身の将棋経験は殆どなく、興味も薄い。
小学生の頃に、友人の弟が将棋好きで教わったことがある。何度か指すうちに彼を負かして感心されたが、友人が転校してからは一度も将棋はしていない。
その時にはきちんと覚えた駒の動かし方も、すっかり忘れてしまった。
縁台将棋の石破レベルですらないので、タイトルの名称も知らなければ玉と王の違いも分からない。大盤解説の大きな将棋盤も、石破と同じく「あのホワイトボードみたいなやつ」という認識でいた。
そんな石破の無知を、佐野が「知らないということは、おそろしい」だの「感覚がわからない」だの、一般常識欠落者のごとくいちいち大仰に反応するのは少々鼻につく。
当然、作中に出てくる対局の描写も、☖と☗の違いもよく分からないまま斜め読みせざるを得ず、その点は作品を味わう上で非常に勿体なかったと思う。
ちなみに下巻の初版は、☖と☗の大半が入れ替わっているそうで、中央公論新社の特設ページに正誤表が出ている。編集部のミスとのことだが、自分のような将棋音痴ならいざ知らず、将棋ファンからすると興ざめだっただろう。
駒の価値

将棋と同様に駒の価値もまったく分からないが、教わった友人宅にあったのは祖父から譲り受けたという木製の盤と駒だった。駒生地は木理の目立たないもので、駒字は書かれていたか彫られていたかは覚えていない。
弟くん曰く「全然高いものじゃない」そうで、遠慮なく扱うよう言われたが、最初に触ったのがそれなりにちゃんとしたものだったのは感謝している。
数年後、懐かしくなって玩具だったかプラスチック製の折りたたみ盤と駒を触ってみたら、音も感触もまったく違って驚いた。
将棋も駒も門外漢ではあるが「駒は指してこそ生きる」と東明が言う意味はよく解る。
駒は楽器や革と同じなのだろう。
初代菊水月作の駒は、自分にとってのスタインウェイのピアノである。
腕が数段上がったのではないかと錯覚するほど指に馴染む鍵盤。指先から零れ出る真珠のような音。
日常的にグランドピアノには触れていたが、最上のピアノはこれほどまでに違うものかと、あの感覚は今でも忘れられない。
いつか自分のものにしたいという憧れと所有欲を掻きたてるところも、まるで同じだ。
天童将棋駒伝統工芸士「掬水」作の駒も、写真画像で拝見しただけだが、盛り上げた駒字が素人目にも非常に美しかった。愛好者からすれば垂涎の的、高嶺の花だろう。
これが飴色になるまで使い込まれたら、どんなに美しいかと見てみたくなった。
何かの拍子に手に入ることがあれば、駒を育てるために将棋を始めるだろうと思うのは、道具フェチだからかもしれない。
上巻は★5
作品名「盤上の向日葵」と、上条桂介の異名「炎の棋士」とくれば、当然ゴッホが思い浮かぶ。
向日葵は桂介の記憶を彩るヒマワリの花だろうと予測し、そのエピソードとゴッホがどう絡んでくるのか楽しみにしていた。
作品は石破と佐野が冬の天童市を訪れるシーンから始まるが、以降は真夏の捜査と真冬の桂介の幼少期が交互に描かれる。
小気味のよいテンポで話は進み、上巻ではヒマワリもゴッホも出てこない。ついでに言えば東名も登場しない。
白骨死体は誰なのか。駒の足取りは。
東大卒で成功したという桂介は、ろくでもない癖に粘着する父親からどう逃れたのか。
丹念に書かれた上巻は、休憩も挟まず貪るように読んだ。面白かった。
帯紙に「2018年本屋大賞2位」とともに書店関係者の賞賛の声が並ぶのも頷ける傑作ミステリだった。
…上巻は。
ちなみに同年の本屋大賞1位は辻村深月『かがみの孤城』。
3位に今村昌弘『屍人荘の殺人』が選ばれている。
年間ベストセラーは東野圭吾『ラプラスの魔女』『人魚の眠る家』がトップ2。
下巻で凋落

息つく間もなく後半では黒衣を翻して真っ赤な裏地を見せつけるように、作者による鮮やかな種明かしがあるものと胸を躍らせ下巻を手にとった。
冒頭で突如現れるヒマワリと母親の記憶。そして桂介とゴッホ(の画集)との出会い。
ゴッホの描く向日葵が儚い亡き母そのもの、というイメージは個人的には頷けないが、そこは人それぞれ。思い直し読み進めたが、ゴッホの解釈にあまり深みが感じられない。
ゴッホの弟・テオの妻ヨーは、ゴッホの死後、彼の知名度向上に貢献したが、同時に兄弟を美化しすぎたとの批判も受けており、また「ゴッホ」というコンテンツとして見ると、あまりにも有名であるがゆえに使い古されている感もある。
そこを柚月裕子はどう料理するのかと期待していたのだが、通り一遍の「狂気の人」「死への希求」が語られるばかりで、「ひまわり」の中で最も有名な15輪を使わず、あえて12輪を選んだ程度のこだわりしか見当たらない。
「盤上に向日葵を咲かせる」構想ありきで、単に「向日葵と言えばゴッホ」を置きに行っただけのように感じられてしまった。
さらに桂介をその型に嵌めようとしている無理やり感に、急速に冷めてしまった。
下巻の半ば辺りで、桂介が自身の半生を振り返り、母の狂気とともに「死への憧れと恐怖」を語り始めた時にはプラスチック製の駒を掴まされたような嫌な感覚があった。
桂介は唐沢夫妻に支えられつつも自力で幼少期を生き延びた。
誰よりも生きること、将棋を指すことに貪欲であり、恵まれた頭脳と才能を使い自分の足で立って歩いてきた。
その桂介が「子供のころからずっと、なぜ自分はこれほど死に強い関心を抱くのか」とは、取ってつけたようではないか。
さらに頭痛とともに盤上に向日葵が咲き、最後まで消えない花が指すべき手であり、「自分のなかの狂った血が、その手を求めている」とは説得力に欠け、些か強引かつ唐突だった。
庸一が桂介の実父ではないことは薄々予想がついていたものの、春子が実兄と通じて桂介を身籠ったという設定は、悪いとは言わないが「盤上に咲く向日葵」に結びつけるための、それっぽいエキセントリックな小道具にしか感じられなかった。
このチープさであれば「桂介の本当の父親は東名で、将棋の才能は実父譲り」でも驚かない。
余談ながら春子の出身が島根県の東部なのは、作者が目指した「将棋界を舞台にした『砂の器』」を意識したのだろうか。実在する「亀嵩」ではなく、宍道湖畔の架空の地名「湯ヶ崎」だけれども。
エンディングについて
エンディングに関しては、特に文句も違和感もないが、意外性もない。
庸一の失踪については知らぬ存ぜぬが通るだろうし(実際何も知らされていないわけだから)、死体遺棄罪であれば刑事罰としては3年以下の懲役なので執行猶予がつくだろうし、大金持ちでもあるのだから、ふてぶてしく生きていけばいいのにとは思うが、「死への希求」を掲げていた以上は、妥当な結末だろう。
素朴な疑問と簡単なメモ

白骨死体とともに見つかった駒袋は正絹製とのことだったが、絹は天然繊維であるため、化学繊維と比べて虫やカビの害を受けやすい。基本的に水にも弱く洗うのも気を遣う。
そんな繊細な素材で作られた駒袋が、3年もの間、腐敗していくご遺体と土中に埋められ無事であるものだろうかと単純に疑問に思った。
それから、佐野が石破に命じられて調べたものの徒労に終わった名物駅弁調べは何だったのだろう。
普通に考えれば石破の、よく言えば豪放磊落、悪く言えば無神経で自分勝手な人となりを表すエピソードだが、もしかしたら無関係な無駄足を積み重ねる刑事としての粘り云々を印象づける狙いかもしれないぞ、と深読みしてみたりしたが、美味しそうな駅弁の数々に消し飛んだ。
そしてもう1つ。
石破のモデルは、まさか衆議院議員の石破茂氏ではあるまいなと思いつつ、四角張った骨太な容姿や日焼けした強面が重なってしまうともう駄目だった。
石破刑事の嫌味ったらしい台詞などは、ずっと石破議員の口調で再生されていた。
まとめ
本作が連載された2015年から2017年は、藤井聡太(現・竜王)が史上最年少(14歳2か月)で四段昇段(プロ入り)を果たした。
2018年には羽生善治 竜王を破り、殊に大きな注目を集めた時期と言える。
一方、作者の柚月裕子は2008年、第7回『このミステリーがすごい!』大賞の大賞を受賞し作家デビュー以来、破竹の勢いで人気作を生み出し続けている。
本作は日本将棋連盟の飯島栄治(現・八段)が監修を行い、2018年に将棋ペンクラブ大賞・文芸部門:優秀賞を受賞。文庫の下巻には羽生善治(現・日本将棋連盟会長)が解説を寄せている。
2019年9月にはNHK BSプレミアムでドラマ化、また2022年10月からコミックウォーカーとニコニコ静画の「COMIC_Hu」にてコミカライズされており、柚月裕子の代表作とも言われている。
作品の背景は華々しいことこの上なく、レビューも高評価ではあるが、個人的には終盤の失速が痛かった。
連載中、各所向けにあれこれ「映え」を狙うような変更があったのではと疑ってしまった。
特に終盤の壬生との対局は感情的な短文の一行が並び、無理やり感満載のゴッホ、そして咲かない向日葵。
対局については将棋を知っている読者であれば、また違う感想を持つかもしれないが、自分としては申し訳ないが何の茶番だと怒りがわくほどだった。
序盤の知識欲を刺激する将棋の描写は読み応えがあり、桂介と唐沢夫妻の交流などもよかったが、盤上に向日葵が咲くというアイデアが十分に書き切られておらず、残念感が否めない。
「柚月裕子」と「将棋」、いわば人気2大ブランドに下駄を履かせられた作品、というのが自分の読後の印象である。





