「犬に与えてはいけない食べ物」シリーズ。今回は「貝」です。
貝はお味噌汁やお吸い物、お刺身やお鮨などの和食から、リゾットやパスタなど洋食まで、色々な料理に使われます。
人間にとっては身近な貝類ですが、犬に与えても大丈夫なのでしょうか?
絶対に与えてはいけない貝

犬は元々、海洋生物の消化がうまくできません。特に貝類を消化する酵素をまったく持っていないため、消化不良を起こす可能性が非常に高いのです。
生の貝類は消化不良のほか、「チアミン欠乏症」などを引き起こす可能性があるため、絶対に与えてはいけません。
また加熱したとしても、一部の貝の内臓には「光線過敏症」を引き起こす物質が含まれていることがあります。
少量なら与えてもよいとされる貝類もありますが、基本的に貝は犬に与えない方がよい食材です。
| 食品 | 生食 | 加熱 | 注意点 |
| アワビ | × | × | 生の内臓(中腸腺)に含まれる「フォエホルビドa」という物質が皮膚炎の原因になることがある |
| 赤貝 | × | × | チアミン欠乏症の原因になる可能性がある |
| ウニ | × | × | チアミン欠乏症の原因になる可能性がある 生ウニにも塩分が含まれ、犬にとっては過多になる場合がある |
| サザエ | × | × | 生の内臓(中腸腺)に含まれる「フォエホルビドa」という物質が皮膚炎の原因になることがある |
| つぶ貝 | × | × | 中毒成分を含むため与えない |
| トコブシ | × | × | 生の内臓(中腸腺)に含まれる「フォエホルビドa」という物質が皮膚炎の原因になることがある |
| トリ貝 | × | × | 生の内臓(中腸腺)に含まれる「フォエホルビドa」という物質が皮膚炎の原因になることがある |
| バイ貝 | × | × | 中毒成分を含むため与えない |
チアミン欠乏症とは?
「チアミン」とはビタミンB1のことです。
エネルギーの産出・代謝など多くの生化学反応に関与しており、神経・心臓の正常な機能に必要不可欠です。
哺乳動物は、体内でチアミンを生成することができないため、食物から摂取する必要があります。
欠乏すると疲労感に襲われ、重度の欠乏症(脚気)では、神経・筋肉・心臓・脳に影響が及び、最終的には死に至ります。
生の魚介にはチアミナーゼが含まれる
「チアミナーゼ(旧称「アノイリナーゼ」)」は、淡水魚・貝類・微生物などに存在するビタミン B1分解酵素です。
腸管内で食物中のビタミンB1を破壊するため,チアミン欠乏症の原因となります。

この酵素は加熱すると失活するため、魚介類は十分に加熱して与える必要があります。
カニ・イカ・タコ・エビ・貝類にも、チアミナーゼは含まれます。
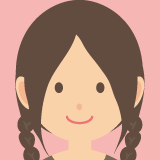
ドライフードは長期保存中にチアミンが分解されやすいので、なるべく新しいフードを与えましょう!
光線過敏症とは?

貝類の生の内臓に含まれる「フェオホルビドa」(「フェオホルバイドa」「フェルフォーバイドa」とも呼ばれる)というクロロフィルの一種が、紫外線に反応することにより引き起こされます。
症状としては、皮膚に腫れやかゆみが出て、犬がかきむしってしまい、毛が抜けます。重症化すると耳が壊死します。
特にアワビ・サザエ・トコブシ・赤貝・トリ貝などは注意が必要です。
また貝は2月~5月にかけて、毒素をため込む性質があり、危険度が高くなります。
トコブシ

トコブシはアワビによく似た、手のひらに乗るくらいの巻貝です。「フクダメ」「ナガレコ」などとも呼ばれます。
夏が旬ですが、おせち料理にも登場します。炊き込みご飯や塩蒸し、缶詰にも利用されます。
赤貝

内湾や浅海の泥底などに生息している二枚貝です。
血液中に哺乳類と同じヘモグロビンを持つため、身が赤く、名前の由来となっています。
晩秋から春にかけてが旬です。寿司ネタや刺身、佃煮などで食されます。
A型肝炎ウイルスを保有する個体が確認されており、専門職が採取したもの以外は、加熱が不十分だと感染するリスクがあります。
トリ貝(トリガイ)

名前の由来は、食用にする足が鳥のくちばしのような形状をしていること、また味が鶏肉に似ていることからとも言われます。
旬は春と秋。国産は流通漁が少なく、高級な二枚貝です。 生でも食べられますが、湯通しして寿司ネタや刺身にします。

何で光線過敏症が重症化すると耳が壊死するの?
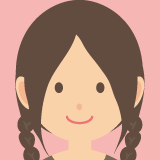
耳は皮膚が薄いから影響を受けやすいんだって
与えてもよいが注意が必要な貝

少量であれば、犬に与えることのできる貝類もあります。
| 食品 | 生食 | 加熱 | 注意点 |
| あさり | × | △ | 2~3個程度を細かく切って与え、様子をみる 貝類の中でビタミンB12を最も多く含む うまみ成分のコハク酸が含まれ、食欲増進が期待できる |
| カキ(牡蠣) | × | △ | チアミン欠乏症の原因になるので基本的に与えない 加熱したものをごく少量であれば問題ない場合もある 手作り食のミネラル、特に亜鉛を補う目的で与える |
| しじみ | × | △ | 肝臓・腎臓の働きを助けるオルニチンを含む タウリン・鉄・亜鉛も含んでいる しっかり砂抜きをして、加熱して与える |
| ハマグリ | × | △ | チアミン欠乏症の原因になる可能性があるので、与えすぎに注意する |
| ホッキ貝 (ウバガイ/姥貝) |
× | △ | チアミン欠乏症の原因になる可能性があるので、与えすぎに注意する |
| ホタテ | × | △ | 加熱した貝柱を少量与える 貝柱は高タンパク質で、ビタミン・ミネラルが豊富 生・水煮・乾燥いずれの商品も塩分を多く含む 貝柱以外の部分は犬にとって有毒なので与えない |
与えるポイント
少量を与える
ドッグフードを主食としている場合は、トッピングやおやつとして与えます。1日の摂取カロリーの10%以内にとどめます。
手づくりごはんの場合でも、他の食材と組み合わせ、トッピングやスープとして与えましょう。
必ず加熱する

与えてもよい貝でも、生の状態で摂取すると、チアミン欠乏症になる可能性があります。
与える場合は、十分に加熱します。
小さく切る
どの貝も小さく切って与えます。
特に小型犬の場合は、喉に詰まらないように細かく切ります。
アレルギーに注意
貝を初めて与える時は、ごく少量を与えて様子を見ます。
以下の症状が現れた場合は、アレルギーが疑われるので、動物病院を受診しましょう。
- 下痢
- 嘔吐
- 皮膚のかゆみ
- 目の充血
ホタテに注意

貝柱以外はNG
ホタテは、加熱した貝柱と貝ひも以外、与えてはいけません。
貝ひもは消化がよくないため、細かく切ります。
もし貝柱以外の部位を食べてしまった場合、嘔吐・震え・ふらつき等の症状があれば、すぐに動物病院を受診します。
何も異常が見られない場合でも、かかりつけの病院に連絡をして、獣医師の判断を仰ぎましょう。
塩分に注意
ホタテは、生・水煮・乾燥などで市販されていますが、いずれも塩分が多く含まれます。
いずれも真水でよく洗い、必要なら一度ゆでこぼしてから与えましょう。
人間用に味つけされた、缶詰やおつまみ、顆粒だしなどの加工品は、与えてはいけません。
犬用のおやつはOK
貝柱や貝ひもを利用した、犬用のおやつであれば、与えても問題はありません。
アレルギーやカロリー過多に気をつけて、少量を与えます。
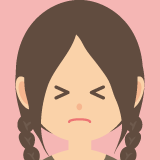
とにかく貝類は加熱が必須!
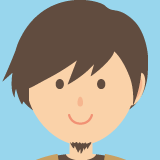
ゆで汁をフードにかけたり、小さく切ったものをトッピングしたりするのがよさそう♪

同じ食材を長期間にわたり摂取することで、後天的なアレルギーを発症する可能性もあるので、他の食材と組み合わせるのも大切かもね
参考:
MSDマニュアル家庭版-チアミン
petokoto「犬は貝を食べても大丈夫? 牡蠣やしじみ、ホタテなど危険性や注意点を解説」
子犬の記念日「犬が食べてはいけない魚 食べていい魚 貝類や海藻類は大丈夫?アニサキスに注意!」
わんちゃんホンポ「犬が食べても大丈夫な魚介類8つ」等
ロイヤルカナン「犬と猫の栄養成分辞典」
ノア動物病院「チアミン(ビタミンB1)欠乏症」
ブリタニカ国際大百科事典「アノイリナーゼ」「中腸腺」
百科事典マイペディア「中腸腺」
ぼうずコンニャクの市場魚貝類図鑑
文部科学省「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ほか



